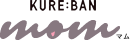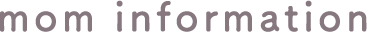コラム
マムコラム:『心を育むマナーの時間』vol.02
『心を育むマナーの時間:和食マナー編』
、
F’sエレガントスクールにてウォーキングやマナーの講師として活動されている内野史子さんによる、
新しいコラムが11月からスタートしましたよ!!ぜひチェックしてみてくださいね♪
、

、
【記事一覧】
*vol.1 お箸の持ち方
*新コラムが始まります
、
、
テーマ《祝箸から伝わるお祝いの心》
、
早いものでもう12月も半ばですね。
、
年の瀬が迫り、新年の準備が少しずつ始まる頃でしょうか。
、
今回は、新年の祝いの席などで使われる「祝箸(いわいばし)」についてご紹介いたします。
、
祝箸はお正月や結婚式、お食い初めなど、特別なお祝いの場で用いられる格の高いお箸です。
、

、
みなさんも、おせち料理やお雑煮などをいただくために用意した経験はありませんか。
、
「お正月は祝箸が置いてあるから何となく使う」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
、
実はとても奥深く、さまざまな意味が込められているのです。
、
お子さんと一緒に「どうしてこのお箸を使うのかな?」と考えてみるのも素敵ですね。
、

、
長さは、末広がり(幸運や繁栄が終わりなく続くことを象徴する言葉)の意味を持つ縁起の良い「八」にちなんで、八寸(約24cm)とされています。
、
材質は、主に柳の白木が使われていたため、「柳箸(やなぎばし)」とも呼ばれます。
、
柳の木は、春一番に芽吹き、しなやかで折れにくく丈夫なことから、縁起が良いとされています。現在はひのきや杉なども多く使われているようです。
、
また、中央のふくらみが米俵に見えることから、豊かな収穫を願って、「俵箸(たわらばし)」と呼ばれることもあります。
、
一般的な割り箸と比べてみましょう。
、

、
祝箸は両端が細くなっています。
、
これは、「片方は神様が、もう片方は私たち人間が使う」という特別な意味が込められており、「両口箸(りょうくちばし)」とも言われています。
、
神様と人が共に食事をすることを神人共食(しんじんきょうしょく)といい、神様に捧げた祝いの膳を、私たちがいただくことで新しい年の健康や幸運を祈ることを意味しています。
、
そのため、自分が使っている箸をひっくり返して取り箸として使うのは、控えることが一般的です。
、
元旦に使った祝箸は、三が日まで、または松の内(1月7日または1月15日まで)の間は、洗い清めて使い続けると言われることもありますが、現在はライフスタイルも様々です。
、
個々の暮らしに合わせてお使いになれば良いのではないかと思います。
、
使用後の処分については、神社でのお焚き上げに持って行ったり、ご家庭で塩で清めて、半紙や新聞紙などに包んで処分したりといった方法があります。
、


、
箸袋には華やかなものが多く、伝統を感じるものから
、

、
かわいらしくおしゃれなものもたくさん出ています。
親子で祝箸について話しながら準備するのも楽しそうですね。
、

、
祝箸を手に取るときには、その由来や意味に思いを馳せ、大切に扱ってみてください。
、
お子さんと迎える新年が、よりいっそう豊かなものになることでしょう。
、
次回(1月)は、
「お箸の扱い方」をテーマにお届けします。
ぜひご覧ください。
、

。
、
毎月15日配信予定ですので、ぜひご覧ください。
、
【記事一覧】
*vol.1 お箸の持ち方
*新コラムが始まります
、
。
《プロフィール》
、

、
内野史子さん
社会福祉士/精神保健福祉士/ウォーキングインストラクター/マナー講師
2009年 F’sエレガントスクール開校。
呉市を中心に活動中。
正しい姿勢と美しい歩き方の講座やビジネスマナー講座、コミュニケーションについての講座などを開講している。